
【賃貸管理会社必見】収益アップを実現する付帯サービス活用術
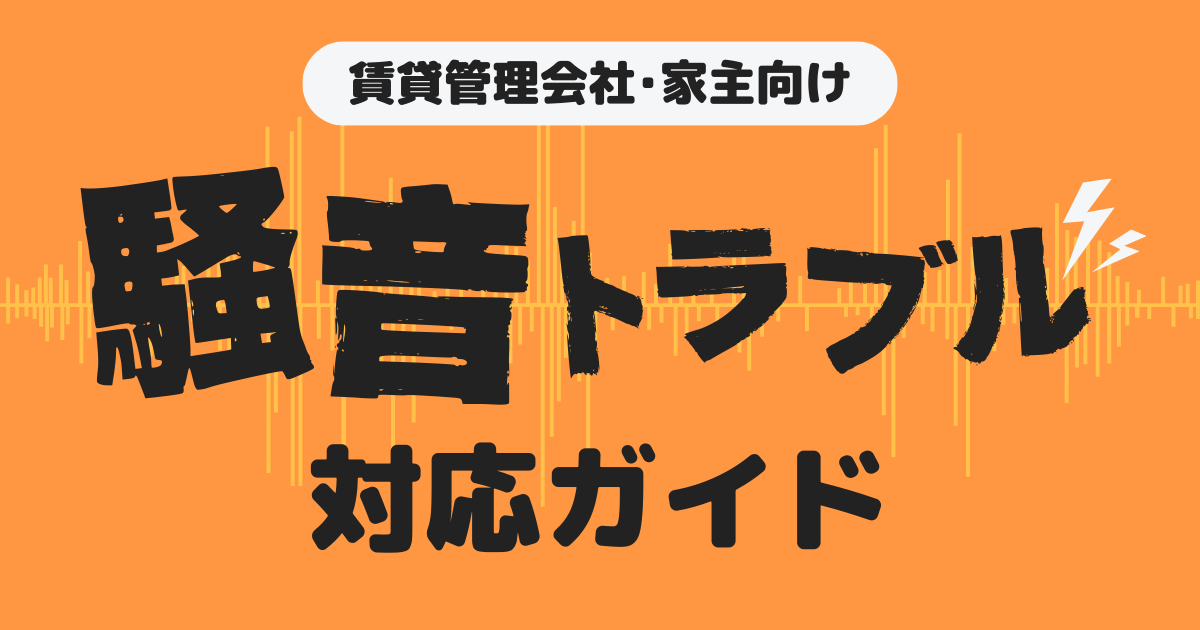
✓なぜ騒音トラブルは放置してはいけないのか
✓騒音トラブルの現状
✓賃貸物件で多い騒音トラブルの種類と原因
✓騒音トラブルが引き起こすリスク
✓騒音トラブルの基本的な対応フロー
✓騒音トラブルを未然に防ぐ方法
✓騒音トラブルの対応に悩んでいるなら
賃貸物件での騒音トラブルは集合住宅の構造や住民の生活リズムの違いにより、どうしても発生しやすい課題です。こうした問題を放置すると、入居者の不満が蓄積し退去につながったり、物件の評判が下がって収益にも悪影響を及ぼしたりします。 本記事では、騒音トラブルが発生した際の具体的な解決策と、問題を未然に防ぐための工夫を解説します。入居者が安心して暮らせる環境を維持し、物件運営を安定させるための参考にしていただければ幸いです。
賃貸物件における騒音トラブルは、最も相談件数が多く、かつ深刻化しやすい問題のひとつです。管理会社や家主にとって「些細な生活音」と捉えがちな場面でも、入居者にとっては大きなストレスとなっており、対応の遅れが退去や悪評拡散、訴訟リスクにまで発展することも少なくありません。
こうしたトラブルを「入居者同士の問題」として放置してしまうと、管理責任が問われたり、信頼を損ねる結果にもなりかねません。特に管理業務を委託されている管理会社の場合は、オーナーとの信頼関係にも影響を及ぼします。
また、SNSや口コミサイトの普及により、対応の良し悪しがすぐに可視化される今、一件のトラブルが物件のブランド価値を左右することもあります。
逆に言えば、騒音トラブルへの丁寧かつ迅速な対応は、入居者からの信頼を高め、退去抑制や空室率改善にも繋がる大きなチャンスでもあるのです。
本記事では、賃貸物件で発生しがちな騒音トラブルについて、
・よくある原因や法的観点
・初動対応の手順
・予防策や外部サービスの活用法
などを整理しながら、家主や管理会社が今すぐできる具体策をご紹介していきます。
▼家賃保証・その他サービスの詳細が知りたい方はこちら!
サービス紹介資料をメールで受け取る
賃貸物件では、騒音トラブルが特に集合住宅で頻発する傾向があります。環境省の「近隣騒音に関する状況調査」によれば、近隣騒音に関する苦情の約60%が集合住宅で発生しているとされています。
その主な要因となっている音には生活に伴う不可避なものが多いため、住民間での感覚の違いからトラブルに発展することがあります。特に集合住宅では、隣室や上下階からの生活音が原因で、入居者の約3人に1人が何らかの不満を感じているとの報告があります。
このような背景から、騒音トラブルへの迅速で適切な対応は、物件運営の安定に欠かせない要素といえます。入居者満足度を向上させるためには、トラブルの原因を正確に把握し、適切な対応策を講じることが重要です。
参考:環境省「令和4年度騒音規制法等施行状況調査」
参考:国土交通省「集合住宅における居住者の音環境評価に関するオンライン調査報告書」
騒音トラブルは、賃貸住宅における最も身近なストレス要因のひとつです。
しかも「加害者が騒音を出している自覚がない」ケースが非常に多く、本人に悪気がないことがトラブルの長期化や感情的対立を招く要因となっています。
ここでは、騒音トラブルの主な種類と、発生の背景となる構造的・生活的な要因を整理します。
集合住宅では以下のような音がトラブルの原因になりやすいとされています。
これらはすべて「日常生活に必要な行為」に含まれますが、音の感じ方には個人差が大きく、受け取り方のズレがトラブルの引き金となります。
ある人にとっては「気にならない音」でも、別の人にとっては睡眠や仕事の妨げになるストレスとなることがあります。特に、在宅ワークが増えた方、高齢者や単身者 などは静寂を求める傾向が強く、生活音への耐性も人一倍低くなる傾向があります。
そのため、単なる“生活音”がクレーム化することも珍しくありません。
騒音トラブルの背景には、生活スタイルだけでなく、建物の性能や間取り、家族構成の違いといった構造的な要因もあります。
| 要因 | 内容 |
|---|---|
| 建物構造 | 木造・軽量鉄骨造はRC造に比べて遮音性が低く、音が響きやすい傾向があります。 |
| 生活リズム | 夜勤明け・早朝起床など、ライフスタイルのズレが騒音ストレスに直結します。 |
| 家族構成 | 小さなお子様がいる世帯では、足音や声、夜泣きなどが原因になりやすくなります。 |
こうした構造・環境的な要因が重なると、「誰が悪い」という単純な問題では済まないケースが多くなるのです。
▼家賃保証・その他サービスの詳細が知りたい方はこちら!
サービス紹介資料をメールで受け取る
騒音トラブルは「入居者同士の問題」として軽視されがちですが、適切な対応を怠ることで家主・管理会社にまで重大なリスクが及ぶことがあります。ここでは、放置によって起こり得る法的責任と運営面での影響を整理します。
民法第601条には「賃貸人は賃料を受け取る代わりに、入居者に目的物(物件)を使用収益させる義務を負う」と明記されています。
これはつまり、「入居者が平穏に暮らせる環境を提供しなければならない」ということです。
騒音トラブルを把握しながらも放置した場合、以下のようなリスクが発生します:
・使用収益義務違反と見なされる可能性
・管理不備を理由とした損害賠償請求
これらは、物件経営の根幹を揺るがす問題に発展しかねません。
「騒音」として法的に問題となるかどうかの目安に、「受忍限度(じゅにんげんど)」という考え方があります。
これは、「社会生活を営むうえで通常我慢すべき音の範囲を超えているか」を判断する基準で、具体的にはデシベル(dB)値での測定が参考にされます。
| 時間帯 | 騒音基準値(環境省) |
|---|---|
| 昼間(6:00〜22:00) | 55dB以下 |
| 夜間(22:00〜6:00) | 45dB以下 |
例えば、掃除機や洗濯機の音(60〜70dB)、ピアノや布団叩き(80dB以上)などは、基準値を上回る可能性があり、法的なトラブルに発展することもあります。
騒音トラブルを放置すると、次のような悪影響が現実的に起こり得ます。
これらは「早く対応すれば防げるリスク」でもあります。だからこそ、初期対応の質とスピードが問われるのです。
騒音トラブルを放置すると、入居者が住み心地を損ねて退去を選択する可能性が高まります。空室期間中の家賃収入が減少し、収益面での影響は避けられません。新しい入居者を募集するにも広告費や仲介手数料が発生し、運営コストの増加につながります。
騒音トラブルへの対応が不十分だと、物件や管理会社に対する悪い口コミが広がる可能性があります。SNSや口コミサイトでの評判は、次の入居者の物件選びに大きく影響するため、一度評判が下がると物件の魅力が損なわれ、空室率の上昇を招きます。
騒音が改善されないまま放置されると住民同士のトラブルが深刻化し、最終的に訴訟や警察沙汰にまで発展することがあります。こうした場合、管理会社や家主にも対応が求められ、精神的・時間的な負担が生まれてしまいます。また訴訟となれば弁護士費用などの金銭的負担も発生します。
騒音トラブルの対応には、状況の確認や入居者への連絡などに多くの時間と労力が必要です。これが他の業務に支障をきたす場合もあります。また、外部機関や専門家への相談が必要なケースでは、追加の費用も発生するでしょう。こうした負担を軽減するためにも、早期対応と適切な解決策が重要です。
▼家賃保証・その他サービスの詳細が知りたい方はこちら!
サービス紹介資料をメールで受け取る
騒音トラブルの対応において最も重要なのは、感情的な対立を避けながら、段階的かつ冷静に対応を進めることです。
ここでは、現場でそのまま使える「5ステップの対応フロー」を解説します。
騒音トラブルが発生した際は、迅速な初動対応が非常に重要です。
まず騒音の種類や頻度、発生時間帯を把握し、詳細を記録することから始めましょう。被害を訴える入居者へのヒアリングを丁寧に行い、騒音計や録音機器を活用して客観的な証拠を収集することで、今後の対応がスムーズになります。
以下のような項目を整理して確認しておきましょう。
・騒音が気になり始めた時期
・音の種類(足音、話し声、家電など)
・発生時間帯(特定の曜日・時間帯か、常時か)
・音の方向・場所(上下階、左右、特定の部屋か)
【注意点】
・クレームが「過敏な反応」である可能性もあるため、先入観を持たずに客観的に記録することが大切です。
・他の入居者にもアンケートや聞き取りを行うことで、複数人の証言を得て客観性を高めるのがベストです。
騒音の原因が特定できても、まずは全入居者に向けて注意喚起を行います。
【対応方法の例】
・共用部への掲示板貼り出し
・各戸ポストへの文書投函
この段階では特定の部屋を名指しせず、以下のような内容に留めると角が立ちません。
「最近、◯時〜◯時の時間帯に生活音に関するご相談が寄せられています。お心当たりのある方はご配慮いただき、今後とも快適な住環境づくりにご協力ください。」
【ポイント】
・書き方は丁寧かつ中立的に。
・攻撃的な表現は避け、自覚を促す内容にとどめましょう。
全体への周知でも改善が見られない場合、騒音の発生源とされる入居者に直接改善を依頼します。
この際、相手の立場や状況に理解を示しつつ、騒音問題の影響を具体的に伝えることが効果的です。管理会社や家主が中立の立場で対応することで、当事者間の感情的な衝突を防ぎやすくなります。
【伝え方の例】
「近隣の方から◯時頃に音に関するご相談が寄せられております。念のためお伺いさせていただいておりますが、何かお気づきの点などございますでしょうか?」
・相手に自覚がないケースも多いため、いきなり責めずに、事実を丁寧に伝えるのが鉄則です。
・騒音の証拠(録音・記録など)がある場合は、必要に応じて提示すると理解を得やすくなります。
状況がさらに悪化する場合や解決が難しい場合は、弁護士やトラブル解決の専門サービスを活用することを検討してください。
地域の騒音基準や条例を確認し、法的な視点を取り入れることで、より効果的な解決策を講じることができます。必要に応じて第三者の協力を得ることで、問題が長期化するリスクを軽減できます。
最後に忘れてはいけないのが、被害を訴えた入居者への対応報告です。
・どのような手順で対応を行ったか
・相手入居者の反応や今後の対応方針
これらを簡潔に伝えることで、「ちゃんと動いてくれた」と安心感を持ってもらえます。報告を怠ると、「放置された」「無視された」と感情的な不信につながりやすいので要注意です。
▼家賃保証・その他サービスの詳細が知りたい方はこちら!
サービス紹介資料をメールで受け取る
騒音トラブルは、起きてから対処することよりも「起こさせない工夫」がはるかに重要です。日々の運用や設備面での工夫を取り入れることで、トラブルの発生自体を大幅に減らすことができます。
この章では、家主・管理会社が実践できる予防的な取り組みを3つの視点から紹介します。
最も基本で効果的な対策は、「音に関する注意事項を契約書や入居時に明文化すること」です。
【記載すべき例(禁止事項・ルール)】
・大音量でのテレビ/音響機器の使用禁止
・ピアノなど楽器の演奏は20時まで
・隣室に響く可能性のある振動・音に配慮すること
さらに、契約時に渡す「騒音トラブル防止パンフレット」や、定期的な案内文などで周知を図るのも効果的でしょう。
過去のトラブル事例や騒音が発生しやすい状況について共有することで、入居者自身がトラブルを予防する意識を持ちやすくなります。
建物の構造や築年数に関わらず、簡単に取り入れられる防音アイテムのアドバイスも効果的です。
【代表的な防音グッズ】
・厚手の防音カーペットやマット
・椅子/テーブルの脚カバーやフェルト
・音響機器の下に防振パッド
・家具(本棚など)を壁に沿って配置することで音の吸収効果を得る
これらを「管理会社からのアドバイス」として案内すると、入居者との信頼構築にもつながります。
また、物件の防音性能を高めるためのリフォームを検討したり、防音性に優れた設備を備えた物件であることを積極的にアピールすることも、入居者に安心感を提供するポイントです。
騒音問題は、被害者が声を上げるまで発覚しづらいという性質があります。だからこそ、トラブルの“芽”を早期にキャッチする仕組みが重要です。
【活用したい工夫例】
・匿名の意見箱(共用部に設置/デジタルでもOK)
・定期的な入居者アンケート
・AI騒音検知センサー(スマートアパート化の一環として)
こうした仕組みがあることで、入居者も「相談しやすい」と感じ、深刻化する前に対処のチャンスが生まれます。
騒音トラブルを未然に防ぐ取り組みは、入居者が快適に暮らせる環境を提供するだけでなく、物件の評判や運営の安定にもつながります。これらの方法を積極的に活用して、トラブルのない物件運営を目指しましょう。
▼家賃保証・その他サービスの詳細が知りたい方はこちら!
サービス紹介資料をメールで受け取る
騒音トラブルは繊細な問題である一方、対応には時間・労力・精神的コストがかかります。管理会社や家主がすべてを自力で対応し続けるのは現実的ではありません。
そこで注目されているのが、騒音トラブルに特化した外部サービスの活用です。ここでは、実際に利用できる代表的なサービスと、その活用メリットをご紹介します。
騒音トラブルが解決しない場合や、迅速な対応が求められる際には、専門的な支援サービスを活用することが効果的です。その中でも、警察のOB・OGによる近隣トラブル解決支援サービス「マモロッカ」がおすすめです。
「マモロッカ」でも騒音トラブルに関する相談は全件の53%を占めており、それゆえに対応実績も多いです。
また騒音トラブルに限らず、ストーカー・DV被害、不法侵入、近隣からの嫌がらせ・迷惑行為、強引な勧誘セールス、SNS誹謗中傷といった、警察ではなかなか介入しづらい入居者の近隣トラブルを幅広くサポートしています。
管理会社や家主がトラブル対応する負担を軽減しながら、入居者にも安心感を提供できます。ぜひ検討してみてください。
▼「マモロッカ」に関するお問い合わせはこちらから!
マモロッカ・その他関連サービスについて話を聞いてみる
騒音トラブルは、どんなに管理体制が整っていても完全に防ぐことはできない生活上の課題です。だからこそ重要なのは、「トラブルが起きたときにどう対応するか」です。
入居者にとっては、問題そのものよりも「相談したあと、きちんと向き合ってくれたか」という姿勢が印象に残ります。
対応スピード × 丁寧さ = 信頼
本記事でご紹介した内容をふまえると、管理側が意識すべきポイントは次の3点に集約されます。
*初期対応を迷わず、速やかに動くこと
騒音トラブルは放置が一番危険です
被害が深刻になる前に、スピード重視で着手を
*感情ではなく、事実ベースで動くこと
被害者・加害者の立場に偏らず、冷静な判断を
複数の入居者の意見を聞く姿勢も信頼につながります
*ルール整備・外部連携・予防策で「起きにくい環境」を整えること
契約時の説明、日常的な注意喚起、仕組みづくりが肝心
必要に応じて専門家や支援サービスを活用する柔軟さも大切です
トラブルの裏には、「対応への不満」が積もっているケースがほとんどです。誠実な対応を積み重ねることで、入居者からの信頼が生まれ、結果として選ばれる物件になります。
特に口コミやSNSの影響が大きい今の時代、トラブル対応の質そのものが、物件ブランドを左右するといっても過言ではありません。
「いえらぶ安心保証」では、万が一の滞納リスクをカバーするだけでなく、外国人・高齢者・生活保護受給者など、多様な入居者にも安心してご対応いただける保証体制を整えています。
騒音・迷惑行為のリスク対策としても、 近隣トラブル支援サービスとの併用がおすすめです。
▼家賃保証・その他サービスの詳細が知りたい方はこちら!
サービス紹介資料をメールで受け取る
この記事を書いた人
いえらぶパートナーズ編集部
私たちは、「親身なサービス×ITで、関わる人すべてを幸せにする」を理念に事業を展開しています。 不動産会社、家主、ご契約者向けに、家賃保証サービス「いえらぶ安心保証」、24時間駆け付けサービス、クレジットカード決済サービスなどを提供し、人と人との繋がりを大切にしています。 ITを活用して感動的なサービスを提供し、賃貸住宅の入居前後のサービス連携やペーパーレス化・キャッシュレス化の推進を通じて、不動産業界全体の発展を目指しています。 このメディアでは、日々の業務で得た気づきやノウハウを発信し、家賃保証業界向けに有益な情報を提供しています。
人気の記事
新着記事
Media | メディア