
「ペット可」で成功する賃貸管理術!設備、ルール、トラブル対策は?
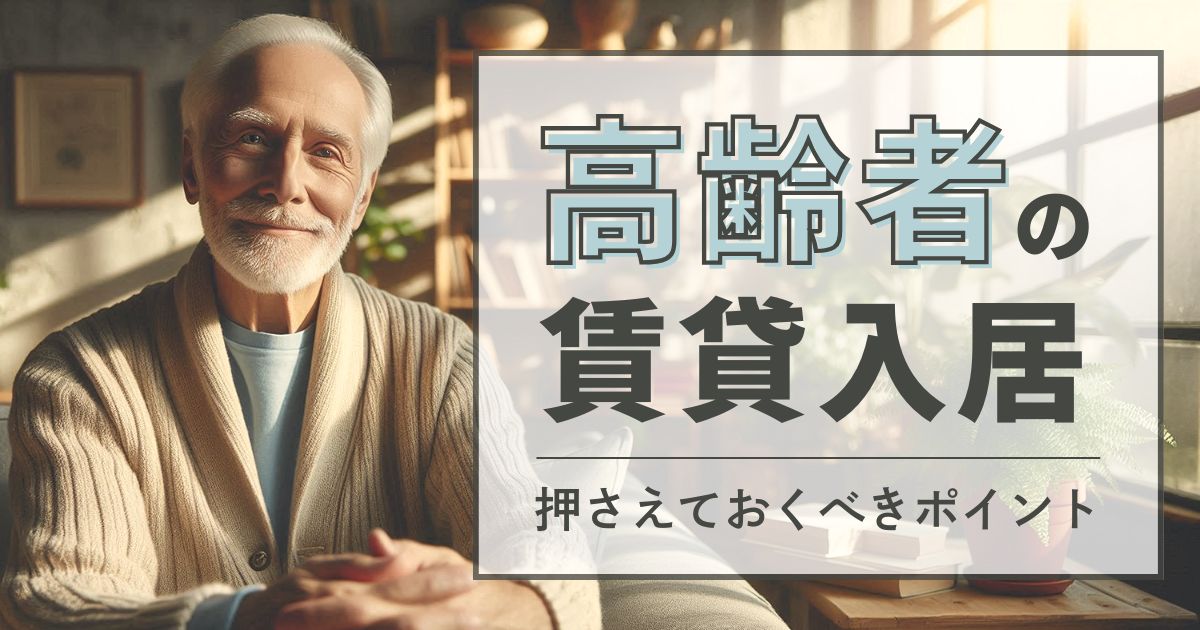
日本は急速に高齢化が進んでおり、65歳以上の人口は増加の一途をたどっています。総務省のデータによると、2024年9月15日時点で高齢者人口は3625万人、総人口に占める割合は29.3%と過去最高を更新しました。2025年には約3,657万人が高齢者となり、単身世帯の割合も年々増加しています。(出典:総務省統計局「統計トピックスNo.142」)
これに伴い、高齢者向けの賃貸需要も高まっているものの、多くの賃貸オーナーや管理会社は「家賃滞納」「健康リスク」「孤独死」などの不安から、受け入れに消極的な姿勢をとっているのが現状です。
本記事では高齢者の賃貸リスクに焦点を当て、発生しやすいトラブルや、それらを回避するための具体的な対策について詳しく解説します。リスクを理解し、適切な対策を講じることで、高齢者の受け入れを安心して進める方法を考えていきましょう。
高齢者の賃貸入居には、多くのメリットがある一方で、オーナーや賃貸管理会社にとって考慮すべきリスクも存在します。特に、「家賃滞納」「健康リスク」「火災リスク」「契約・相続の問題」などは、トラブルに発展する可能性があるため、事前に対策を講じることが重要です。
高齢者の多くは年金生活を送っており、毎月の収入が限られています。そのため、家賃の支払い能力に不安を感じるオーナーも少なくありません。また、高齢者の中には連帯保証人がいないケースも多く、滞納が発生した際に回収が困難になるリスクがあります。
さらに、年金の受給日が家賃の支払日とずれていることが原因で、一時的な滞納が発生するケースもあるため、オーナー側で柔軟に対応できる仕組みを整えておくことが求められます。
対策
・家賃保証会社の利用:高齢者向けのプランを提供している保証会社を活用することで、万が一の家賃滞納時もオーナーのリスクを軽減できる。
・事前の資産チェック:預貯金や年金の受給額を確認し、安定した収入源があるかを審査時にチェックする。
・家賃引き落としの仕組みの工夫:年金受給日後に支払日を設定するなど、柔軟な対応を検討する。
高齢者は転倒や急病のリスクが高く、特に一人暮らしの場合、孤独死の懸念があります。東京都監察医務院のデータによれば、東京23区内で一人暮らしの65歳以上の方の自宅での死亡者数は、令和2年に4,238人と報告されています。(出典:内閣府「令和4年版高齢社会白書(全体版)」)
孤独死が発生した場合、物件の原状回復費用や心理的瑕疵の影響により、次の入居者募集が難しくなる可能性があります。
対策
・見守りサービスの導入:人感センサーやスマート家電を活用し、入居者の異常を早期発見する。
・近隣住民や管理会社とのコミュニケーション強化:入居者との定期的な接触を行い、異変を早期に察知する仕組みを作る。
・定期的な安否確認:契約時に家族や支援団体と連携し、定期的な連絡体制を整える。
高齢者の認知機能低下や身体的な衰えによって、火災の発生リスクが高まることも懸念点の一つです。東京消防庁のデータによると、住宅火災による死者の約7割が65歳以上とされており(出典:東京消防庁「住宅火災による高齢者の死者が急増中」)、火災の予防対策が不可欠です。
特に、ガスコンロの消し忘れや、電気ストーブの誤使用による火災が多く報告されています。
対策
・火災報知機やガス遮断装置の設置:火災の発生を未然に防ぐため、適切な設備を導入する。
・IHクッキングヒーターへの切り替え:ガスコンロの代わりに電気コンロを使用することで、火災リスクを低減する。
・定期的な設備点検:配線やガス設備の老朽化をチェックし、事故を未然に防ぐ。
高齢者が亡くなった場合、契約の解除や家財の処理がスムーズに進まないことが問題になるケースがあります。賃貸借契約では、入居者が亡くなった場合でも、相続人が契約を引き継ぐため、オーナーが勝手に契約を解除できないという法律上の制約があります(民法第896条)。
また、相続人が不明な場合、物件の明け渡しや残置物の処理が長期化し、賃貸収入に悪影響を及ぼす可能性もあります。
対策
・死後事務委任契約の活用:契約時に、万が一の際の家財処分や契約解除の手続きを明確にしておく。
・相続人の事前確認:契約時に相続人の有無を確認し、連絡先を取得しておく。
・終身建物賃貸借契約の導入:入居者が亡くなった時点で契約が終了する仕組みを取り入れることで、相続問題を防ぐ。
高齢者の賃貸入居には、家賃滞納や健康リスク、契約解除の問題など、オーナーにとって慎重な対応が求められる要素が多くあります。しかし、適切な契約・保証対策、安全対策、保険・公的支援の活用を行うことで、リスクを大幅に軽減することが可能です。ここでは、具体的なリスク回避策を解説します。
可能であれば、親族や信頼できる人に連帯保証人になってもらうことが望ましいです。特に相続人がいる場合、契約時にその連絡先を明確にしておくことで、万が一の契約解除や残置物処理をスムーズに進めることができます。しかし高齢者の場合、連帯保証人を確保できないケースが少なくありません。
そのため、家賃滞納のリスクに備え、家賃保証会社を利用することで万が一の滞納時にも家賃の回収を確保できます。高齢者向けの保証プランを提供している家賃保証会社もあるため、契約時に導入を検討するとよいでしょう。
▼ご高齢者の保証人受入れも可能な家賃保証
「いえらぶ安心保証」について詳しく見る
高齢者の入居において、最も懸念されるのが健康リスクですよね。転倒や急病、孤独死を防ぐためには、事前の対策が必要となります。
近年、人感センサーやスマート家電を活用した見守りサービスが普及しています。例えば、一定時間動きが検知されない場合に管理者や家族に通知が届くといったシステムを導入することで、異変を早期に察知できます。特に、遠方に住む家族がいる場合は、このようなサービスを推奨すると安心です。
また人の手で定期的に高齢な入居者の安否確認を行い、その結果を家族や親族にメールで知らせるシニア見守りサービスもあります。事前にかかりつけ医や介護情報などを個別で電子カルテ化するため、対応するオペレーターも都度適切な対応ができる点が魅力です。入居者本人が困ったときには電話相談も可能です。
加えて近所との交流があることで、万が一の異変に気づきやすくなります。オーナーや管理会社が定期的に入居者とコミュニケーションを取るほか、地域の自治体や近隣住民と協力しながら、見守り体制を整えることも重要です。
高齢者の事故の多くは室内での転倒によるものです。そのため、手すりの設置や、段差の解消、滑りにくい床材の導入を検討することで、転倒リスクを軽減できます。また、国や自治体が実施する「住宅セーフティネット制度」を活用すれば、高齢者向けの住宅改修や家賃補助を受けられる可能性があります。高齢者が安心して暮らせる環境を整えながら、オーナー側の負担も抑えることができるので是非活用してみてください。
高齢者の入居において懸念される孤独死リスクに対し、原状回復費用や家賃損失を補償する保険が存在します。この保険に加入することで、万が一の際の金銭的な負担を軽減することができます。
▼孤独死保険付帯プランも!
「いえらぶ安心保証」について詳しく見る
高齢者の賃貸入居には、家賃滞納、健康リスク、契約解除の問題などの懸念がありますが、適切な対策を講じることで安心して受け入れることが可能です。特に、家賃保証会社の活用や見守りサービスの導入、孤独死対応保険の加入などを組み合わせることで、リスクを最小限に抑えることができます。
また、高齢者は転勤や転職が少なく長期入居の可能性が高いため、安定した賃貸経営にもつながります。
もし、高齢者の保証人が確保できない場合でも、いえらぶパートナーズの家賃保証サービスを活用すれば、万が一の家賃滞納時にもオーナーのリスクを軽減できます。
これからの時代、高齢者の受け入れは空室対策の一つとして重要な選択肢です。リスク管理を行いながら、安全で安定した賃貸経営を目指しましょう。
この記事を書いた人
いえらぶパートナーズ編集部
私たちは、「親身なサービス×ITで、関わる人すべてを幸せにする」を理念に事業を展開しています。 不動産会社、家主、ご契約者向けに、家賃保証サービス「いえらぶ安心保証」、24時間駆け付けサービス、クレジットカード決済サービスなどを提供し、人と人との繋がりを大切にしています。 ITを活用して感動的なサービスを提供し、賃貸住宅の入居前後のサービス連携やペーパーレス化・キャッシュレス化の推進を通じて、不動産業界全体の発展を目指しています。 このメディアでは、日々の業務で得た気づきやノウハウを発信し、家賃保証業界向けに有益な情報を提供しています。
人気の記事
新着記事
Media | メディア