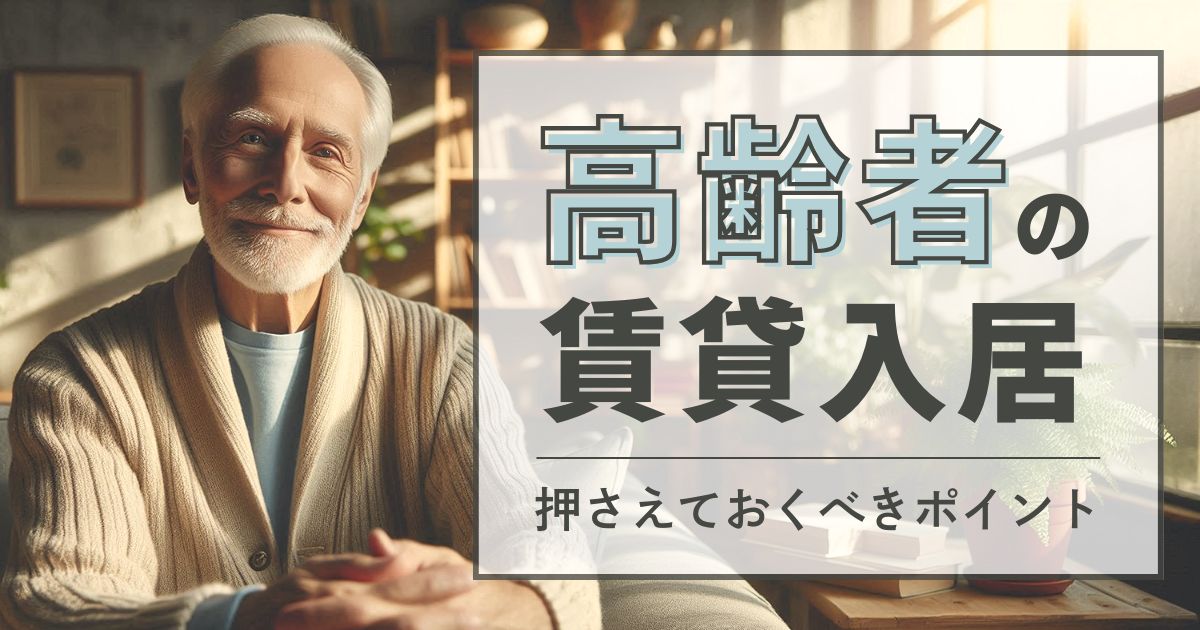
高齢者の賃貸入居はリスク?賃貸経営で押さえておくべきポイント
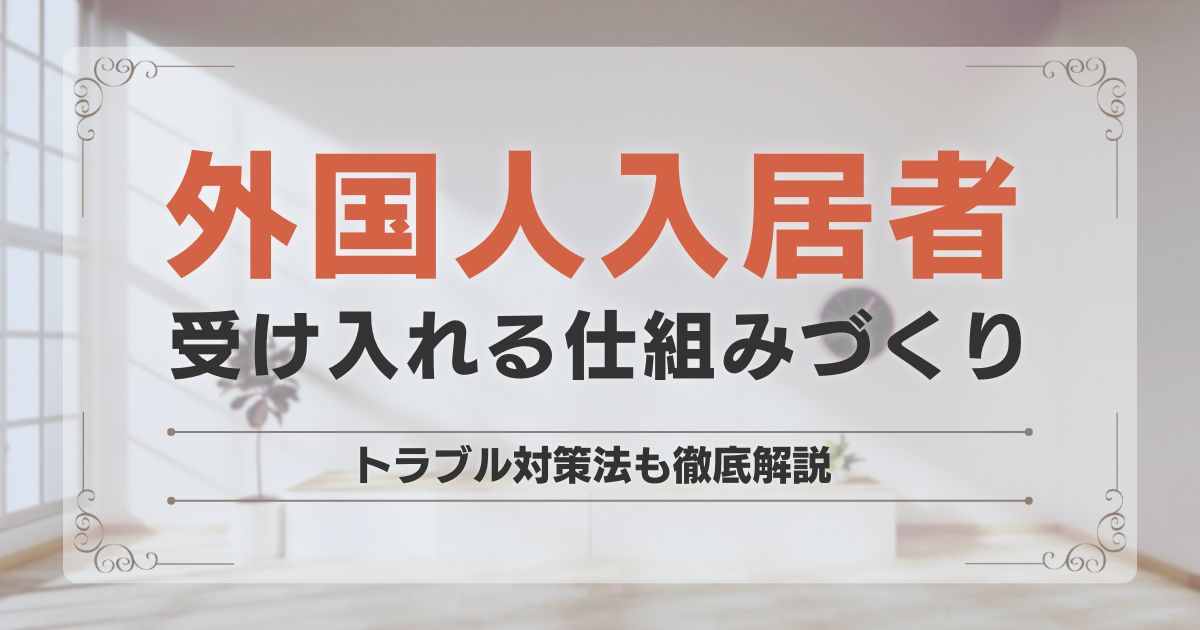
✓外国人入居者を受け入れるメリット
✓外国人入居者を受け入れてよく起こるトラブル
✓外国人入居者を受け入れるためのトラブル対策
✓外国人入居者への対応を強化するなら
✓外国人入居者の受け入れ体制を整えるならいえらぶ安心保証
▼外国人入居者とのトラブルを未然に防ぐ具体策をご紹介!
外国人入居者受け入れマニュアル
少子高齢化が進み、賃貸物件の空室対策もより一層強化していかなければいけないと悩んでいませんか?
最近は解決策の1つとして、外国人の受け入れが注目されています。
2024年の在留外国人数は358万人を超え、過去最高人数を更新しました。(出入国在留管理庁調べ)コロナ禍が収束しつつある今、外国人需要はさらに増加する見込みです。都市部に限らず、地方都市でも外国人の居住ニーズは高まりを見せており、「外国人対応できる物件」は今や差別化ポイントにもなりつつあります。外国人を受け入れることで、収益の安定だけでなく、多様性を取り入れた賃貸経営が可能になります。
しかし同時に、「文化の違い」や「言語の壁」などに不安を抱く声も少なくありません。
本記事では、そうした不安を払拭するために、外国人入居のメリットとリスク、そして具体的なトラブル対策や成功事例をわかりやすく解説していきます。
日本では少子高齢化が進み、空室が増えていることが大きな課題です。一方、2024年には在留外国人数が358万人を超え、外国人の賃貸需要が高まっています。
しかし外国人が入居できる物件はまだ少なく、供給が追いついていません。そのため外国人を受け入れる体制を整えることで、空室を減らせる可能性が高いです。また外国人は一度住むと長く滞在する傾向があります。賃貸物件を見つけるのが難しいため、簡単に引っ越ししないことが多いのです。
外国人を受け入れる物件が少ない中、「多言語対応」「外国人フレンドリー」という点は、他の物件と差をつける大きなアピールポイントになります。
多言語対応の契約書を用意したり、生活ルールをわかりやすく説明したりするだけでも大きな利点です。外国人のニーズにも応えることができる物件として認識されるため、物件価値が上がり、競争力を高めることができます。
外国人コミュニティはネットワークが強い傾向があります。そのため、一人の外国人入居者が物件を気に入ると、友人や知人に紹介してくれることがよくあります。留学生や労働者の間では特に情報共有が活発で、口コミを通じて次の入居者を見つけることができるのです。
宣伝費用を抑えつつ入居者を増やせるのも大きなメリットです。
▼外国人入居者とのトラブルを未然に防ぐ具体策をご紹介!
外国人入居者受け入れマニュアル
外国人入居者の受け入れにはさまざまなメリットがある一方で、文化や言語の違いによるトラブルも想定しておく必要があります。
ここでは、入居前・入居中・退去後の3つのフェーズに分けて、代表的なトラブルとその背景を紹介します。
日本独自の慣習である「礼金」や「更新料」は、海外にはない制度であるため、契約時に戸惑う外国人が少なくありません。
「なぜ謝礼を払う必要があるのか?」「更新時に追加料金が発生するのはおかしい」などの声が上がることもあります。
【対策】制度の背景や意味を、母国語や図解付き資料で丁寧に説明することが重要です。
一部の国では「光熱費込み」が一般的なため、日本の「別請求」スタイルを理解してもらえないことがあります。
【対策】共益費と光熱費の違いを明確に伝える資料を用意しましょう。
地域ごとに異なるゴミ分別ルールは、日本人でも難しいことがあります。
外国人にとっては「曜日ごとに袋を分ける」「指定の袋を買う」などが非常に複雑に感じられ、結果としてルール違反が発生しやすくなります。
【対策】多言語対応の案内+入居時オリエンテーションでの徹底が有効です。
外国では深夜に友人を招いてパーティーを開く文化も多く、騒音に対する認識の違いがトラブルの原因となります。
【対策】音の感じ方や日本の生活マナーについて、具体例を交えて説明しましょう。
「友人が一時的に泊まる」「家賃を割り勘にしたい」という感覚で、無断で同居・転貸を行うケースも。
【対策】契約書に「同居・又貸し禁止」の特約を明記し、同意を得ることが必要です。
ペット可否の意識や、部屋を自由に模様替えできるという価値観の違いも原因になります。
【対策】禁止事項を具体的に説明し、写真付き資料で明示するのが効果的です。
一概には判断できませんが、外国人労働者や留学生は、帰国に多くの経費がかかることや経済状況の変化といった事情から家賃滞納のリスクが高いと言えます。
経済的な事情に加え、支払いスケジュールの認識違いや、国際送金の遅延などが要因になることもあります。
【対策】家賃保証会社の利用や、自動引き落としの導入が有効です。
「敷金=全額返金されるもの」と考えていたり、「香辛料の匂い」「壁の傷」は通常使用と認識されていたりと、感覚のズレが大きな原因になります。
【対策】入居時に「どこまでが入居者負担か」を具体例付きで説明しておくと安心です。
急な帰国や強制送還などで、連絡が取れないまま退去されるケースも。荷物を置いたまま帰国されることもあります。
【対策】緊急連絡先や退去後の連絡手段を事前に確認しておきましょう。
これらのトラブルは、悪意があって起こるものではなく、ほとんどが「文化の違い」や「日本のルールを知らないこと」が原因です。
言葉や常識が違うからこそ、事前の説明やフォロー体制が何より重要になります。
外国人入居者には、在留資格が切れたまま不法滞在してしまうケースがあります。また保証人制度の理解が難しい外国人も多く、日本特有の制度に適応できない場合があります。
万が一不法滞在者を受け入れた場合には、家主も責任を問われる可能性があるため、在留資格や必要書類の確認が重要です。
▼外国人入居者とのトラブルを未然に防ぐ具体策をご紹介!
外国人入居者受け入れマニュアル
外国人入居者を受け入れる際のトラブル対策は、事前準備と入居後の適切な対応が鍵となります。ルールを明確に伝えることや、信頼できるサポート体制を整えることで、トラブルを防ぎながら賃貸経営を安定させることが可能です。
安心して外国人入居者を迎え入れる環境を整えましょう。
外国人入居者を受け入れる際は、何より事前準備が重要です。
まず国土交通省が提供する「外国人の民間賃貸住宅入居円滑化ガイドライン」を活用しましょう。このガイドラインには、在留資格の確認方法や必要な書類、入居時のルール説明のポイントが多言語で記載されています。
また在留資格やパスポートを確認することで、不法滞在やトラブルのリスクを未然に防ぐことができます。契約書や生活ルールも多言語で用意し、文化や言葉の壁を越えたスムーズなやり取りを目指しましょう。
入居時には、ゴミ分別や騒音防止など、日本独自の生活ルールを徹底的に説明することが大切です。図やイラストを使った案内資料を用意することで、視覚的にわかりやすく伝えられます。
またペット飼育や改装禁止などの禁止事項を具体的に説明し、外国人入居者から同意を得ておきましょう。
トラブルが起きた際には、早期発見と迅速な対応が鍵となります。外国人向けのコールセンターや多言語対応の保証会社を活用すれば、言葉の壁を感じることなく問題を解決しやすくなります。
また外国人入居者だけでなく、近隣住民からの意見を吸い上げやすい環境づくりも重要です。小さな問題でも早めに認識し直接コミュニケーションを取ることで、大きなトラブルに発展するのを防げます。
外国人入居者が賃貸物件で暮らす中で困った際に頼れる相手がいれば、大きなトラブルになる前に問題を解決しやすくなります。
自社で外国人入居者支援を強化するのも良い対策ですが、幅広く入居者サポートを行う業者を使って「困ったらここに連絡してください」と案内するだけでも、外国人入居者にとっては頼り先ができて安心材料の1つになるかと思います。
▼外国人入居者とのトラブルを未然に防ぐ具体策をご紹介!
外国人入居者受け入れマニュアル
外国人入居者を受け入れる体制だけ整えることができれば、今後増えていくであろう外国人人口に比例して空室も埋めやすくなるかと思います。ただ、外国人入居者の受け入れ体制を自社だけで創り上げていくのはなかなか骨が折れるのではないでしょうか。
ここでは、実際に導入する際の準備項目と、役立つ支援ツール・サービスをご紹介します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 契約書の多言語対応 | 英語、中国語、ベトナム語などで準備 |
| 入居ルール説明資料 | 図やイラストを使った資料で、生活マナーを伝える |
| 生活ルールチェックリスト | 入居時に確認&署名をもらう |
| 緊急連絡先の確認 | 本人・企業・母国の連絡先を取得しておく |
| 保証会社の利用 | 外国人対応可能な家賃保証会社を選定 |
| コールセンターの導入 | 多言語でのトラブル一時対応を外部に委託 |
店頭で外国人入居者に説明をする際に、スマホやパソコンで通訳と電話をつないで会話できるサービスです。
伝えることが難しい契約内容や家賃の支払い方法なども、通訳の方からしっかり伝えてもらうことが可能です。
複数の言語に翻訳されたショートムービーで、契約から退去までに起こりうる手続きやトラブルを分かりやすく解説します。
視覚的にも訴求できるので、言葉で説明するだけよりも理解してもらいやすくなります。
文化の違いにより、どうしてもトラブルが起こってしまうかもしれない…。
そういった不安があれば、トラブルの際に第三者が介入して解決支援してくれるサービスもつけておくと良いでしょう。これは外国人入居者を受け入れる際に、同じ建物に住む入居者へのケアにもなります。
▼外国人の入居受入れも安心!
外国籍プランの家賃保証内容を見てみる
外国人入居者の受け入れには、契約書の多言語化やトラブル対応、在留資格の確認、保証人の確保など、通常以上の準備や配慮が求められます。
しかし、すべてを自社だけで対応しようとすると、人的コストも精神的負担も決して小さくはありません。
そこでおすすめしたいのが「いえらぶ安心保証」。あらゆる審査基準を設けて審査し、問題なければ外国人入居者も積極的に受け入れている賃貸保証サービスです。
11ヵ国語に対応した「いえらぶ通訳」を利用でき、外国人入居者の店頭対応もスムーズになります。スマホやPCで三者間通話をすることにより、通訳がその場にいるかのように会話可能です。
また、6ヵ国語に対応した重要事項説明動画の案内をいえらぶパートナーズから外国人入居者に送信。契約から退去までに起こりうる手続きやトラブルを分かりやすく説明するので、言葉で説明するだけでは伝わりにくい日本のルールを理解してもらいやすくなります。
家賃滞納時のように密なコミュニケーションが必要な際には、いえらぶパートナーズの国際チームが手厚くフォローします。
▼外国人の入居受入れも安心!
外国籍プランの家賃保証内容を見てみる
本記事では、外国人入居者のメリットやデメリット、トラブル対策を網羅的に紹介しました。
入居前の準備、適切なルール説明といった仕組みを整えつつ、保証会社や外国人対応可能な業者とも連携し、外国人入居者を安心して受け入れられる体制を整えましょう。
今回ご紹介したサービスに関しては、いえらぶ安心保証の付帯商品としてご案内が可能です。
いえらぶ安心保証の代理店様であれば無料で利用できるサービスもあるので、ぜひご覧ください。
▼ 外国人入居者の受け入れ体制を整えたいなら!
いえらぶパートナーズの「いえらぶ安心保証」
▼外国人入居者とのトラブルを未然に防ぐ具体策をご紹介!
外国人入居者受け入れマニュアル
この記事を書いた人
いえらぶパートナーズ編集部
私たちは、「親身なサービス×ITで、関わる人すべてを幸せにする」を理念に事業を展開しています。 不動産会社、家主、ご契約者向けに、家賃保証サービス「いえらぶ安心保証」、24時間駆け付けサービス、クレジットカード決済サービスなどを提供し、人と人との繋がりを大切にしています。 ITを活用して感動的なサービスを提供し、賃貸住宅の入居前後のサービス連携やペーパーレス化・キャッシュレス化の推進を通じて、不動産業界全体の発展を目指しています。 このメディアでは、日々の業務で得た気づきやノウハウを発信し、家賃保証業界向けに有益な情報を提供しています。
人気の記事
新着記事
Media | メディア